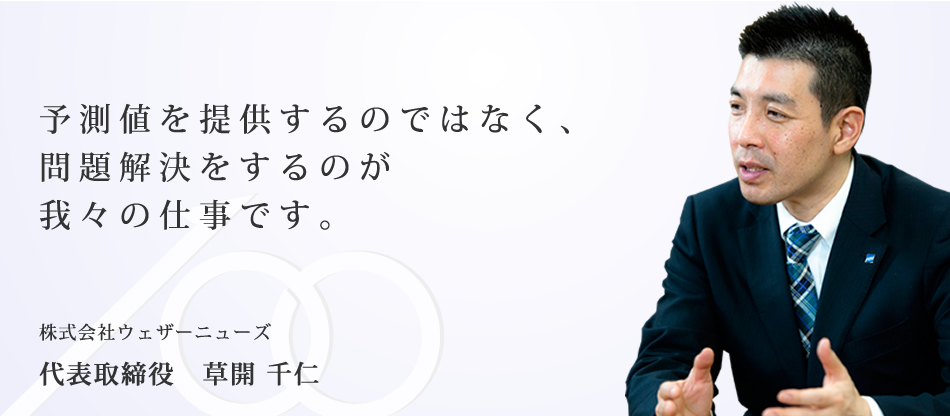![]()
- 1965年
- 東京都生まれ
- 1987年
- 青山学院大学理工学部物理学科卒業
- 1987年
- 株式会社ウェザーニューズ入社
- 1993年
- 営業本部CSS事業部長 就任
- 1993年
- 営業総本部航空事業部長 就任
- 1996年
- 防災・航空事業本部長
- 1996年
- 取締役 就任
- 1997年
- 常務取締役 就任
- 1999年
- 代表取締役副社長
- 2006年
- 代表取締役社長 就任
- “気象”という特有の分野において、御社の成長のストーリーをお聞かせください。
-
私の中で一番大きいのは、当社の創業者である初代社長・石橋の“無常識な発想”です。ウェザーニューズを立ち上げた当初、石橋の同期は口を揃えて「国がやっていることだから絶対にビジネスにはならない」と言ったそうです。月並みな人間であれば諦めるところを、石橋は「国の提供している情報では不十分だ」と、必ず市場が立ち上げられると信じて疑いませんでした。
通常、気象サービスで最も重要なものは予報技術者ですが、ウェザーニューズの場合はマーケティングを非常に重要視しています。現在、ウェザーニューズにいる620名の社員のうち、営業に携わるスタッフは約50名。おそらく、従来の気象事業の中でそれだけ営業を入れるという発想はなかったと思います。市場からの要望は「もっと精度の高い予想が欲しい」というもので、これに対して「はい、わかりました。やります」といったアクションをウェザーニューズがとっていたならば、今日のウェザーニューズの市場はありません。基本となる情報は気象庁から無償で得られるので、それに対して多少精度の高いものであれば、コストとしては限りなく無料に近い金額になります。そこの切り口を変えて、基本無料のものに、完全に違う価値をつけました。例えばある航空会社に対して、単なる空港の予測だけではなく、その航空会社ならではの気象に基づいた、燃料やフライト時間変更などの情報を提供します。そこまで次元を高めていくためには、営業と言うマーケティングの人間が必要になります。物売りとは違って、ウェザーニューズの営業はすべてがマーケティングなので、50人近くの規模できちんと配備して、気象予報よりもちょっといい市場ではなく、完全に新しいマーケットを作りました。 - 成長の大きな要因となったポイントは何でしょうか?
- 成長の大きなキーは3つあります。1つ目のキーは、顧客の問題解決に対するリスクコミュニケーションサービスを行ってきたことが挙げられます。ウェザーニューズの前身であるオーシャンルーツは、船会社に対してルート選定を行う会社でした。波や風を予測するのではなく、波や風を基に最適な航路を選定し、早くから問題解決をしてきました。このコンセプトを飛行機や陸に応用することによって、ウェザーニューズが新たな市場を立ち上げた、と言う方が正しいと思います。予測値を提供するのではなく、問題解決をするのがウェザーニューズの仕事です。
2つ目のキーは、サービスを支えるスタッフです。我々が行っているのは継続のサービスなので、“24時間365日愚直に”運用するスタッフがいないとすぐダメになってしまいます。実際、ウェザーニューズの市場に対して様々な民間気象会社がトライしてきたことがありました。しかし、24時間365日、良いサービスを提供し続けるというのは大変なことです。ウェザーニューズに入社したスタッフは、「いざというとき人の役に立ちたい」という想いで入社した方ですので、そこが結果的にはお客様との信頼に結び付きました。なかなか見えないことかもしれませんが、すごく大きいですね。
3つ目のキーは、スタッフを支えるITインフラだと思います。これも一般的な気象会社としては非常に珍しいのかもしれませんが、我々は創業以来、機械が出来ることはすべて機械で行ってきました。IT技術を使って気象のデータベースを作り、そこからビジュアライゼーションも含めたコンピューターを使ったサービスを行っていました。“24時間365日愚直に”というのは非常に重要ではあるのですが、機械が出来ることまで人間がやり続けると、だんだんと人間が怠惰になって、24時間365日良いサービスを提供するということが続けられなくなります。 - 2番目で仰っていた“24時間365日愚直に”働くというのは理屈で言うと簡単に見えますが、だからこそ他社が出来なかったと思います。御社が出来て他社が出来なかったというのは、一体何が違ったんでしょうか?
-
文化的なところが結構大きいのではないかと思います。24時間365日、立派な気象技術者がサービスを提供し続ける会社は多いと思いますが、その大変さや素晴らしさにハイライトしている会社がどのくらいあるかというのはわかりません。あとは、それが個人の力だった場合、その方が辞めてしまうと、いいサービスは出来ません。それを組織的に出来るようにするノウハウが、ウェザーニューズの中には脈々と流れています。当社と他社の差別化を一言で言うなら、サポーターとの相互信頼ではないかと思います。
- サポーターとは企業と個人のどちらでしょうか?
- 企業サポーターと個人サポーター、双方です。企業サポーターの例でいえば、サービスの発想自体はシンクタンクの方がすぐに思いつくと思いますが、サービス化という部分で、ウェザーニューズとお付き合い頂いているさまざまな方の意見によって、より本当にサービスできる形としてブラッシュアップをします。例えばその意見は、ただ聞けば話して貰えるかと言えば、そうではありません。お客様も暇ではないので、正しい情報をくれる人に聞かないとわかりません。様々なサービスのヒントは市場から出てきます。サービスを検討するというとき、「そのサービスは本当にそのお客様だけの意見なのか?それとも市場全体の意見なのか?」という疑問がわき、それに対してお客様が色々と意見を出してくれる。意見を言って頂けるのは、そこに相互信頼があるからです。意見をくれる企業サポーターというのは、そう簡単には出来ません。昨日今日で作った相互信頼ではないので、ウェザーニューズの非常に大きな財産そのものです。今後大きな成長のベースになると思っているのは、個人サポーターが送って下さる気象の実況リポートです。ウェザーニューズには、有料・無料合わせて、リポート登録して下さっている方が国内で400万人居て、天候によって差はありますが、1日あたり3~5万件くらいの実況レポートを送って下さります。ウェザーニューズは、2004年から蓄積されている気象に対するさまざまなデータを保持しています。その膨大なデータによって、正確な気象予報が出来ます。ウェザーニューズが今後グローバル展開する上で、サポーターの方たちが作った実況リポートと、それを基にして提供する予測と言うのは、ウェザーニューズにとって非常に大きな財産です。
- リポーター登録の際に必要な資格や審査はどういったものですか?
- そういうのがあると敷居が上がって裏目に出るかなと思っているので、特に設けていません。ウェザーニューズの中でも、「一般人に送ってもらったデータがあてになるのか?」という議論はありましたが、そこはむしろ逆で、気象的な知識がなくても、ぱっと見た空の状況などを感じたまま、素直に送ってくれた方がいいのです。観測は“オブザベーション(observation)”と表しますが、ウェザーニューズでは“アイザベーション(eye-servation) ”即ち、“感測”と表現します。実際の観測データももちろん重要ではありますが、その観測データは場所によって異なりますから、サポーターの方たちが寒い、暑いなど、感じたまま送って下さる情報こそ事実なのです。
- サポーターとの相互関係は、どのように築いてこられたのですか?
- これは2つあると思います。まず、ウェザーニューズ自身が「自分たちは気象屋だから、自分たちが正しい」というスタンスをとらないこと。レポーター登録の資格を提示したり、情報の真偽を疑ったりしてしまうと、逆にレポーター側が不信感を抱いてしまうためです。
そしてもう1つは、ウェザーニューズが、「レポーターの情報を価値のあるものにするだけの実力がある」ということを証明し続けるということ。せっかく頂いた情報も、活用しなければ意味がありません。ウェザーニューズが独自に整備したデータと、サポーターから頂いたレポートを加味して的確な予測を立てるなど、活用することに意味があります。こういったデータを保持しておらず、ゲリラ雷雨防衛隊の方たちからの情報をそのまま提供するという形であれば、それこそウェザーニューズを介する必要はなく、直接情報提供したほうがよいのではないかという感覚になってしまいます。ウェザーニューズがウェザーニューズなりに調べ、その結果及ぼす影響を割り出すところまで価値を高められる会社だからこそ、サポーターの方の「自分が送ったものが社会の貢献につながる」という実感につながり、レポートを送って下さるのです。今は「SOLiVE24」という番組を通じて、サポーターから送られた情報がどういったことに役立ったのかという話をするようにはしてします。それはすごく重要だと思います。 - 第4期、2012年頃からの話をお聞かせください。
- 第4成長期は、一言で申しますと、「交通気象をグローバルに展開する」ということが非常に重要な、ウェザーニューズなりの見解です。海は確かにグローバルに展開していますが、空ないしは陸、特に我々が展開しているのは交通気象です。ビジネス的にもそうですが、ウェザーニューズの使命としても、第3期までに整えた、「陸・空の交通気象を10年間かけてグローバル展開しよう」ということになりました。最初はアジアから始めて、次にヨーロッパ、最後はアメリカ。これを実現するために、我々は運営上で「三極体制」という非常に大きなテーマを持っています。今、ウェザーニューズは基本的に幕張のグローバルセンターから全世界を見ていますが、日本からの運営という点に対して、ヨーロッパやアメリカのお客様は「同じ陸地にいないのにわかるのか」という感覚があります。実はオクラホマとオランダには、私たちの仲間がいます。そこでは今、限られた業務だけを行っていますが、この第4成長期にグローバル展開する上で、海・空・陸、三極でフルサービスが出来る体制を作る必要があります。これが、グローバル展開を行う上で重要な1つ目のポイントです。
2つ目は、グローバルにおけるマーケティング力の人材強化です。現地採用の場合、マインドの悪い人間はいなくとも、そこまでアグレッシブな人たちというのはあまりいません。そこにはあまり注力していなかったのですが、今後必要となってくるので、今は1ヵ月に2・3人ずつ日本に来てもらい、一緒に仕事をして、共にマインドを高めていきます。現在約50名いるマーケティング担当の営業のうち、約8割は日本人です。そのため、日本におけるマーケティング力は確かにあるのですが、グローバルとなると非常に人数が限られます。グローバルになった瞬間、あの広いヨーロッパを数人で営業するというのは、マーケットのニーズがあってもなかなか応えられません。これまでの成功事例を踏まえて考えると、まずグローバルな市場を立ち上げるための人材強化は、第4成長期においては「待ったなし」だと思います。日本人が行って出来ることではないと思っているので、グローバルなマーケットが出来るスタッフとの出会いのために、ノンジャパニーズの留学生などにインターンに来ていただいて、気に入ったら採用しています。時間が掛かるように見えますが、それが一番手っ取り早いですね。中途ですと、ある種の癖がついてしまっていることが多いためです。
3つ目がITです。IT技術が重要なため100名のスタッフがいるとお話しましたが、それは基本的に日本において勝ち抜くための実力だったと思います。一方、グローバルではグローバルに通用するIT力が求められます。日本は正確さと安定さでは非常に強いのですが、クイック&ダーティに弱く、見た目だけでアメリカに負けるようなことが多いので、そういうところもアメリカに勝てるようなIT技術が非常に必要だと考えています。この辺りはウェザーニューズが内部で新入社員を使って立ち上げるということもありますが、場合によっては良い仲間作りも重要だと思っています。
4つ目は気象インフラです。今後グローバルに展開する上で、独自のインフラが非常に重要になり、それを開発する必要があります。そのために、ウェザーニューズだけの知識や経験では進んでいないので、気象が一番進んでいるアメリカのオクラホマ大学のキャンパス内にオフィスを借り、イノベーションセンターを作り、大学の人達と開発を行っています。
それから、これはあくまで気象の話になりますが、「このシステムバージョンをシリコンバレーに作ったらどうか?」という話も出ています。おそらく、ビジュアライゼーション、コミュニケーション、シュミレーションの部分で運用上十分なものではなく、場合によっては世界でトップへ行くような技術力を付けること。これが、このグローバルの“本当の意味”での大きな成功の鍵になるのではと思っています。 - これが「10年間」の構想ということですね。御社の決算報告書を拝見しますと、3年間増収増益で自己資本率も高い、超優良な業績という印象を受けました。
- それは第3成長期にどれだけ失敗したか、ということだと思います。ウェザーニューズは17期・18期に百十数億の売り上げを出していました。当時は阪神淡路大震災や奥尻津波の影響もあり、ウェザーニューズがあまり知られていなかったなか、当社では防災に対する事業を重要視しました。一方、阪神淡路大震災の影響で国から非常に大きな補助金、つまり一時金を受けました。求められるのであればと、積極的に行っていた背景もありまして、一時期ウェザーニューズの売り上げの1/3以上は、システムインテグレーションの売り上げでした。ところが、システムインテグレーションというのは、お客様ごとに違うものを作る必要があるので、当然内部の人材だけでは足りなくなります。そこで、市場に出ているIT技術者を大量採用した時期もありました。すると、本来ウェザーニューズが行うべきコンテンツの質を高めるということよりも、お客様とコミットして契約しているシステムインテグレーションの方へ皆流れてしまいます。結果、コンテンツ的には変化がなく、システムインテグレーションは次々に依頼がくるので売り上げが上がりますが、それは一時的な売り上げでしたので、当時営業の責任者だった私には、来期の見通しが全く立ちませんでした。
ウェザーニューズが一部上場した最初の年の決算説明会の前に、石橋が「システムインテグレーションをやめる」という大きな決断をしました。「数字的には大きいが、続けていたら10年の経緯を見た時にウェザーニューズがおかしくなるためだ」と。すぐにやめるということは出来ないので、数年かけてやめる。ただし、やめるということは売り上げが落ち、当然赤字になります。「一部上場したばかりにも関わらず赤字の可能性があるけれどもやった方がいい、泥はすべて自分が被る」という話を石橋としたことを、今でも覚えています。私が株主なら、「何のために一部上場したのか」と怒るでしょうけど、そこは石橋自身にも同じ思いがあったとは思います。
その後、ウェザーニューズは有言通り売り上げが落ち込み、赤字になった部分もありましたが、そこはわざとそうしたということになります。そういった試行錯誤があるなかで、「第3成長期のウェザーニューズは“健全性”でいこう」という方針になりました。そういうことで赤字が増えてしまうと、社会全体的に新たな価値や市場展開に対しておっくうになってしまいますが、それはウェザーニューズではありません。健全性というのは、トールゲート・ビジネスモデルという、コンテンツを中心としたものです。そこに集中して上げていけば、そのまま利益になる。利益が上がれば、その利益を通じて、市場に新たな価値を提供することが出来る。それこそ「皆の元気になるんじゃないか」と定義づけ、利益を出すことは悪くないと考えたのです。第2成長期に失敗を経験したことで、第3成長期の意識改革になり、今の第4成長期があります。